【続編】ジーニアス法で何が変わる?米国・日本(JPYC)を横断比較しながら“ステーブルコイン=国債”時代を読み解く
2025年7月18日、米国でGENIUS(ジーニアス)法が成立。ステーブルコインの裏付け資産・開示・ライセンスを明確化し、米国債需要の受け皿としても機能する可能性が注目されています。本記事では、前回の入門編を踏まえ、米国と日本(JPYC)を比較しながら、個人投資家が押さえるべき実務ポイントを整理します。
前回のおさらい:ステーブルコインは「国境を越える安定通貨」
ステーブルコインは「法定通貨に価値連動」し、ブロックチェーンで24時間P2P送金できるデジタルマネー。現金・電子マネー(Suica/PayPay)・暗号資産の良いとこ取りで、特に国際送金・清算で価値を発揮します。
ジーニアス法(米国)の要点:規制の明確化と「国債需要」の創出
- 裏付け資産の厳格化:現金、銀行預金、短期米国債(T-Bill)、FRB残高など流動性の高い資産のみ。
- 開示・監査:準備資産の定期開示とコンプライアンスを義務化。
- 発行体のビジネスモデル:保有者に利息は原則不可→国債利回りの利ザヤが主収益。
- 構造的インパクト:発行量が増えるほど、米国債の安定買い手が増える仕組み。
結果として、「ステーブルコイン=実質的に国債で裏付け」という構図がより鮮明になります。
日本(JPYC)の現在地:同じ“設計思想”、違う“制度の粒度”
日本の円建てステーブルコイン(例:JPYC)も、円預金+日本国債(JGB)など安全資産の裏付けと、利ザヤ中心の収益構造という点で米国と共通します。日本は資金決済法の改正で区分・保全・カストディなど制度の粒度が細かく、透明性に強みがあります。
| 観点 | 米国(ジーニアス法) | 日本(JPYC想定) |
|---|---|---|
| 裏付け資産 | 現金・銀行預金・短期米国債・FRB残高 | 円預金・日本国債(JGB)など高流動資産 |
| 収益モデル | 利ザヤ型(保有者利息なし/国債利回り→発行体収益) | 利ザヤ型(手数料抑制+安全資産運用) |
| 規制の粒度 | 包括法で基準化、開示・監査・ライセンスを要求 | 資金決済法で区分管理・国内保全など詳細ルール |
| 市場インパクト | 米国債の新たな買い手創出(規模インパクト大) | JGBの安定需要の回路創造(段階的に拡大) |
| 主要リスク | 相互依存リスク(ステーブルコイン⇄国債の連鎖) | 制度変更・スケール(普及速度と流動性の確保) |
要するに、設計思想は似ているが、スケールと制度の粒度が違う——というのが実務上の最大ポイントです。
「国債→利ザヤ→発行体→流通拡大」の循環
ユーザー資金 →(発行体)→ 国債購入 → 利回り発生 → 発行体の収益 → マーケ強化・流通拡大 → さらに国債需要へ…という循環ループが生まれます。これは米・日とも共通です。
いんべすた@の実務スタンス(アップデート)
- ステーブルコイン=送金・清算の道具。運用は別レーンで最適化。
- 国債投資は原則短期(〜2年)で金利取り:価格変動リスクを低減。
- 為替と金利の二軸を意識:米ドル建て送金ツールとして活用、円建てはJPYC等で国内回し。
- 預け先の透明性(準備資産・監査・開示頻度)と払戻し条件は毎回チェック。
よくある質問(FAQ)
Q1. JPYCは米国と同じように“国債で裏付け&利ザヤモデル”ですか?
大枠は同じです。円預金+JGBのような高流動資産で裏付け、利回り(利ザヤ)が発行体の主収益源になります。日本は保全と区分管理が厳格で、透明性に強みがあります。
Q2. ドル連動(USDC等)と円連動(JPYC)の使い分けは?
国際送金・ドル決済ではドル建てが便利。国内回り・円建て会計では円建てが管理しやすいです。為替と手数料の総コストで判断を。
Q3. リスクは? 相互依存で“売り”が連鎖することは?
米・日は共に裏付けが国債なので、極端な換金要求や金利ショック時に売却連鎖の圧力がかかる可能性はゼロではありません。発行体の開示・流動性管理と、利用側の分散がカギです。
まとめ:ステーブルコイン=国債の「新しい消化システム」
- ジーニアス法で、“規制の明確化”ד国債需要の自動化”が前進。
- 日本(JPYC)も設計思想は共通、制度の粒度とスケールで色合いが変わる。
- 個人は送金・清算の効率化として使い、運用リスクは国債のデュレーション管理で抑える。
感想・ご質問はコメントへどうぞ。
「このあたりの図解が欲しい」などもお気軽に!
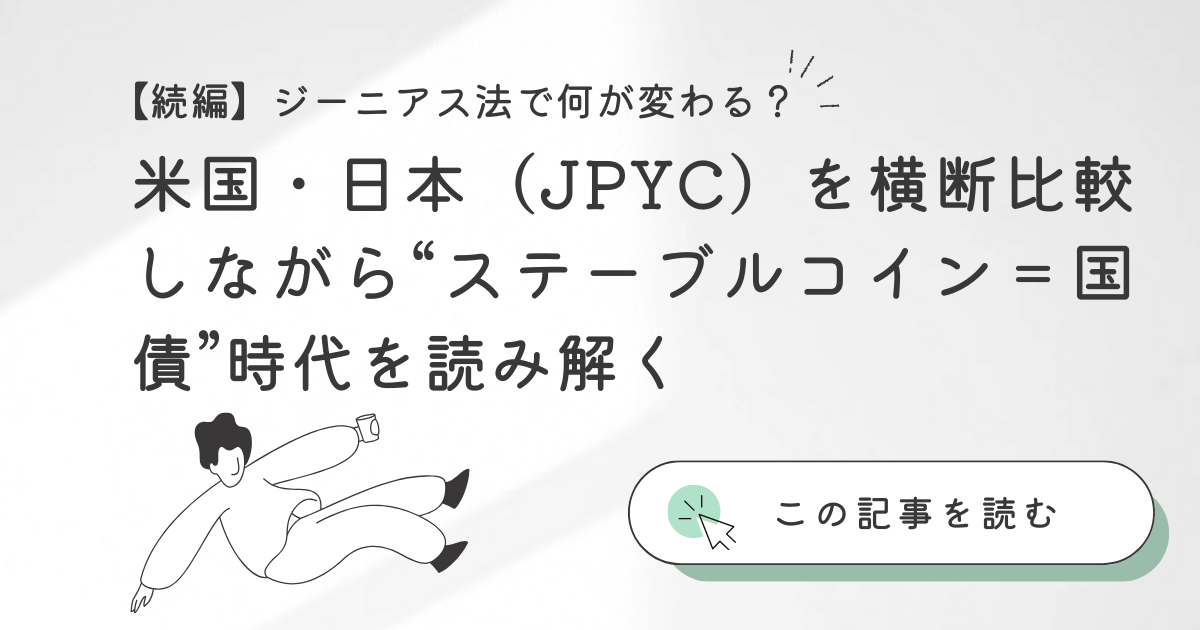
コメント